未経験から金融コールセンターで発信業務に挑戦した50代主婦の体験記です。
「金融コールセンターは大変そう…」と思う方も多いかもしれませんが、実際には資格や金融知識を身につけ、働き方の選択肢を広げるチャンスでもあります。
この記事では、
- 発信業務の仕事内容とリアルな大変さ
- 声の印象を活かすコミュニケーションの工夫
- 証券外務員・生保・損保資格の取得体験とその活かし方
をまとめています。
50代から再就職を考える方や、金融コールセンターに興味がある方の参考になれば嬉しいです。
40代主婦の再就職は「金融コールセンター」から
「そろそろ働かないと」──そう思っても、ブランクの長い主婦にできることは何だろう?
そんな不安から始めた再就職で、私が選んだのは 発信型の金融コールセンター でした。
私が金融コールセンターに再就職したのは40代半ばの頃。
そして今50代になり、そのときに得た知識や資格は、その後の金融事務の仕事や転職活動に大きな武器となっています。
「コールセンターはきつい仕事」というイメージもありましたが、実際に働いてみると 未経験でも挑戦できる入口 であり、さらに金融知識と資格を得られる貴重な場だったのです。
私の経歴と派遣・再就職までの道のり
これまでの専業主婦のあとの職歴はこんな感じです。新卒で入社したのは保険業界でした。その後の職歴は以下の通りです。
- A銀行系コールセンター:6年
- B銀行系コールセンター:1年
- 保険系コールセンター:短期含め2社
- 金融系(ideco)コールセンター:短期
- 金融系事務職:3社
- 現在:銀行での融資事務&電話業務(5年目)
夫は単身赴任、子どもたちの学費もかかる時期。再就職に求めたのは「通勤しやすい・家庭と両立できる」こと。条件に合ったのが、近所の金融系コールセンターでした。
より詳しい転職ストーリーはこちら▼
👉【50代転職のリアル】転職迷子から学んだ“自分に合う働き方と必要なスキル”
金融コールセンターで必須の資格とは?|証券外務員・生保・損保の取得体験
コールセンターでも、金融商品を扱う部署となるため資格が必須です。
私が取得したのは、以下の資格でした。
- 証券外務員(二種・一種)
- 生命保険募集人資格(一般課程試験、専門課程試験、変額保険販売資格試験、応用課程試験、外貨建保険販売資格試験)
- 損害保険募集人資格(基礎単位、商品単位)
子育てと家事をしながらの勉強は本当に大変でした。若いころと違い、アラフォー世代(当時)の記憶力低下も痛感しましたが、同期と励まし合いながら合格を重ねました。
転職先でDCプランナー、ファイナンシャルプランナー(FP)、宅地建物取引士(宅建)などの資格取得を考えたこともあります。
資格については別記事でまとめています▼
👉【50代からの学び直し】中高年でも挑戦しやすい資格まとめ
✅資格を取ったことは、金融コールセンターで働く上で必要条件でしたが、転職活動でも大きな武器になりました。まず履歴書に「証券外務員・生保・損保資格」と書けることは、業界では即戦力となります。若いときに取得したわけではなく、アラフォーになってから勉強して合格したという点も評価されたことがあります。
証券会社や銀行出身者なら外務員資格は当然持っていますが、未経験から挑戦した私にとっては「努力して得た証明」でした。
この経験は「知識を得ただけでなく、続ける力や学び直す力がある」という自己PRにもつながりました。
生命保険募集人資格の特徴(私の時代)
当時は「会社ごとに取り直し」が必要で、転職するたびに試験を受け直しました。
調べたところ「移管」という制度で前職の資格を持ち越せる場合もあるそうですが、私は退職=資格失効となっていました。そのため、新しい会社に入ると再度一般課程試験から受験が必要でした。そのため合計3回受けています。損害保険募集人資格も更新手続きが必要みたいです。
- 移管できない場合 → 試験合格~登録完了まで1〜3ヶ月かかる
- 有効期限があるようで更新手続きが必要
✅なお、生命保険募集人資格や損害保険募集人資格の「移管」や「持ち運び」の扱いは、ケースによる異なる場合、制度や時期によって変わる可能性があります。
実際に受験・勤務を考える場合は、必ず最新の公式情報や勤務先の指示を確認してくださいね。
発信型コールセンターの仕事|声の印象を活かすコミュニケーション術
発信型コールセンターでは、声の印象がすべてです。
研修で学んだのは「笑声(えごえ)」──笑顔で話すことで、声に明るさや安心感が宿ります。
また、心理学で有名な「メラビアンの法則」では、言葉そのものよりも声のトーンや雰囲気のほうが印象に影響する割合が高いとされます。
電話応対はまさにその通りで、「どう話すか」が信頼につながると実感しました。
✅コールセンターでよく研修で使われるメラビアンの法則とは?
「コミュニケーションにおける言語、聴覚、視覚の影響の割合を示す法則のこと。人が受ける印象のうち、言葉の内容はたった7%。声のトーンなど聴覚情報は38%を占める」だそうです。
コールセンターに向いている人とは?必要なスキルと適性
発信型コールセンターの大変さは、受電とは少し違います。
今の時代はそもそも電話に出てもらえないことが多く(笑)、根気よくかけ続けることが前提です。
出てもらえても、すぐに断られることもしばしば。
そこで大切なのは「かける勇気とかけ続ける根気」、そして「慣れ」。
慣れてしまえば、リズムが出来て、体の方で動いてくれるようになります。
ただし、厳しい成約ノルマのある職場はやはりハードかもしれません。件数ノルマだけの環境なら続けやすいと思います。
50代主婦が発信業務を続けられた理由|勇気と根気で乗り越えた工夫
緊張しやすい私は、心の準備なしになかなか架電することはできませんでした。
そこで:
- 顧客履歴を事前に読み込む
- 想定問答を準備する
- クレーム対応時のイメトレしておく
といった工夫を重ねました。こうして「安心材料」を揃えることで、少しずつ度胸と自信をつけていきました。
金融コールセンターで得られたもの|資格・金融知識・コミュニケーション力
- 金融知識:株、投資信託、国債、保険商品など、働きながら実践的に学べた
- 資格:証券外務員・生保・損保資格の取得経験は、後の転職や金融事務で武器になった
- コミュニケーション力:声で伝えるスキルは、その後の事務の仕事や面接でも役立った
発信コールセンターは単調できつい面もありますが、「誰でも挑戦できる入口」であり、「知識と資格を得てキャリアを広げられる場」でもあります。
まとめ|50代からでも金融資格とコールセンター経験はキャリアの武器になる
- コールセンター発信業務は未経験からでも始めやすい
- 金融資格を取ることで、知識もキャリアも広がる
- 資格取得の大変さを乗り越えた経験は、その後の仕事に直結する
「きついだけ」と思われがちな仕事でも、続ければスキルと知識が残ります。
50代からでも、金融知識や資格は必ずキャリアの武器になります。
関連記事はこちらから
👉後に挑戦した【受電メインのコールセンター】は、発信業務とはまったく違う難しさがありました。
【50代派遣の再就職】コールセンター受電体験談|未経験から学んだ即答力と傾聴力
👉金融事務の派遣として働いた体験談です。
【50代派遣の転職体験】金融機関で強みを活かし新設チームで成果を出した話
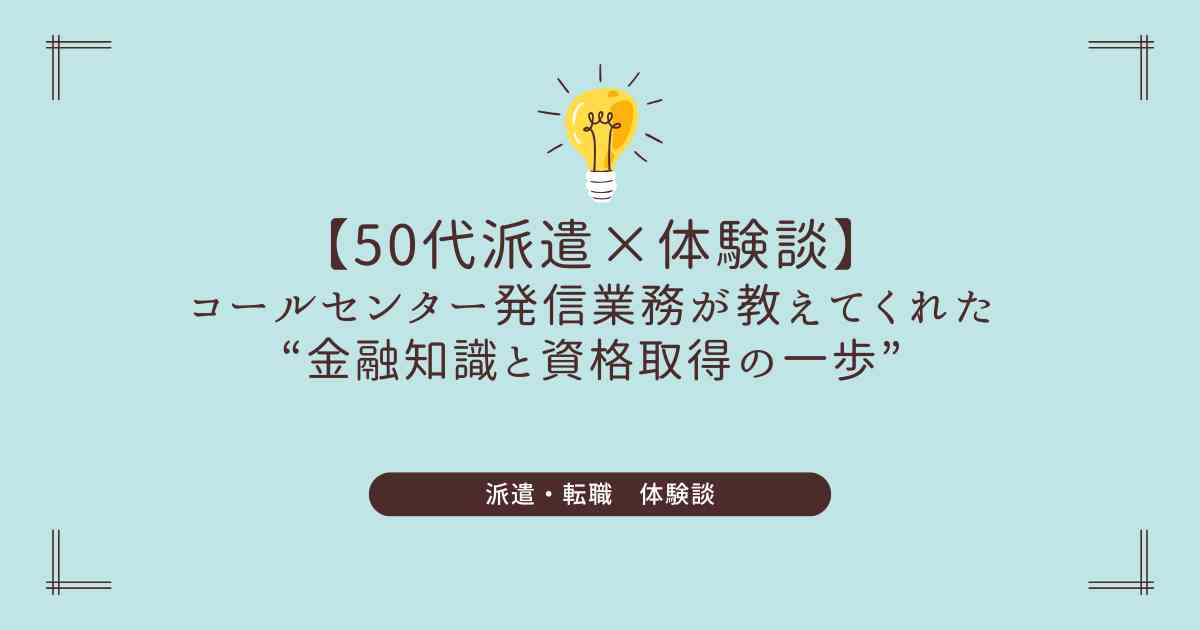


コメント